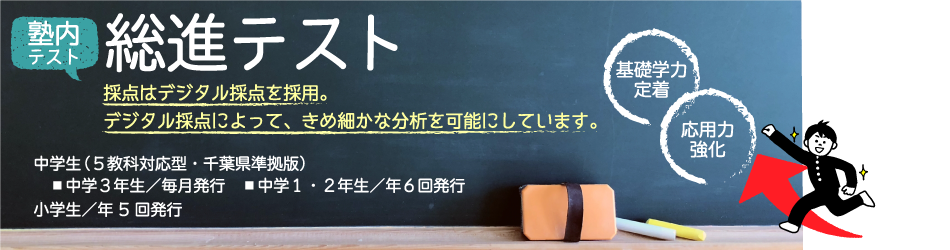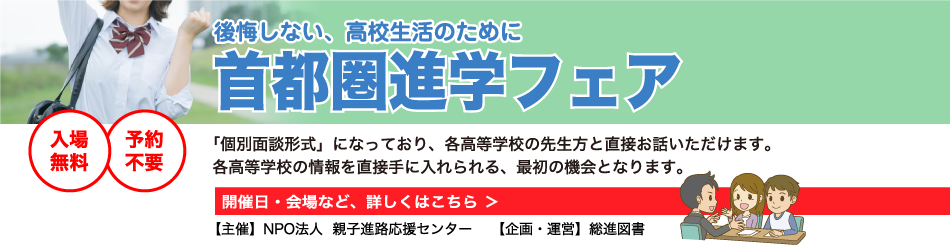一般入学者選抜の検査内容と選抜方法
1.本検査
〔1〕検査内容等
| 検査の内容 | 時間・配点 | ||
|---|---|---|---|
| 第1日 | 【学力検査】 国語・数学・英語 |
国語は、放送による聞き取り検査を含む。英語は、放送によるリスニングテストを含む。 |
国語・数学は50分 英語は60分 各教科100点 |
| 第2日 | 【学力検査】 理科・社会 |
各教科50分 各教科100点 |
|
| 【学校設定検査】 | 各高等学校において、面接、集団討論、自己表現、作文、適性検査、学校独自問題及びその他の検査のうちからいずれか一つ以上の検査を実施する。 | 検査の時間等については、各高等学校が定める。 | |
※定時制の課程において、学力検査を3教科(国語・数学・英語)に定め、学校設定検査を第1日の学力検査終了後に実施した場合、検査期日を第1日の1日のみとすることができます。
【各高等学校が定める検査】の各検査の概略
- ● 面接
学習活動や学校生活に対する意欲・関心、あるいは一般常識を問う検査。 - ● 集団討論
複数の受検者に対して、同一のテーマを与え、司会者を定めないで自由に討論させる検査。 - ● 自己表現
決められた時間内において、あらかじめ受検者が申告するなどした実施形態によって発表をさせる検査。 - ● 作文
指示された題名のもとに、(自由に書かせることを含む)文書を作成させる検査。 - ● 小論文
ある文章や資料等を与え、その全体又は一部について問い、受検者のものの考え方等を見る検査。 - ● 適性検査
専門学科が、その特色に応じて行う実技等の検査で、各学校が指定する実施形態によって行う検査。 - ● 学校独自問題
基礎・基本の定着を見る問題、思考力・応用力を見る問題又は教科横断的な総合問題による検査。 - ● その他の検査
上記以外で、あらかじめ学校が示した方法による検査。
例)・県が作成する思考力を問う問題 ・集団に課題を与えて、活動を観察する検査(集団適性検査)
〔2〕検査時間割
| 本検査 | 第1日 | 第2日 | ||
|---|---|---|---|---|
| 9:30 9:30~ 9:50 9:50~10:05 10:20~11:10 11:40~12:30 12:30~13:15 13:25~14:25 | 集合 受付・点呼 注意事項伝達 国語 数学 昼食・休憩 英語 |
9:30 9:30~ 9:50 9:50~10:05 10:20~11:10 11:40~12:30 12:30~13:15 13:25~ |
集合 受付・点呼 注意事項伝達 理科 社会 昼食・休憩 学校設定検査 |
|
※学校設定検査のうち、県が作成する「思考力を問う問題」を実施する場合は、第2日の午前1時25分から午後2時25分 に行う。
※3教科の学力検査を実施する定時制の課程にあっては、学校設定検査を第1日の午後2時40分以降又は第2日の午前9時 30分以降に行うものとします。
〔3〕選抜方法等
ア 基本的選抜方法(令和7年度入試では、全日制全体の約90%がこの方法で選抜をおこないました。)
「千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項」には、次のように定められています。
- ●中学校の校長から送付された調査書等の書類の審査、学力検査の成績及び学校設定検査の結果を選抜の資料とし、各高等学校の教育を受けるに足る能力、適性等を総合的に判定して入学者の選抜を行うものとする。
- ●調査書の必修教科の評定の全学年の合計値及びその他の記載事項、学力検査の成績、学校設定検査の結果等の選抜の資料は原則として得点(数値)化するものとし、選抜のための各資料の得点を合計した「総合点」に基づき総合的に判定する。選抜の資料の配点は各高等学校において別に定める。
- ●各高等学校の選抜の手順、選抜のための各資料の項目及び配点等を定めた「選抜・評価方法」は、各高等学のウェブページに掲載する。
上記の文章より、選抜は次の4つの資料で行われます。それぞれを数値化し、合計した「総得点」に基づいて合否を決めます。
【学力検査の成績】【調査書中の必修教科の全学年の評定合計値】
【調査書中の記載事項】【学校設定検査の結果】
それぞれの選抜資料は、学校・学科の特色や相対的なバランスも考慮し、次のように定められています。但し、市立高等学校においては、当該市教育委員会が定めるところによります。
【学力検査の成績】
学力検査を実施した各教科の得点を合計し、「学力検査の得点」とします。5教科を実施した場合は、各教科100点ですので、基本的には500点満点となります。但し、「理数に関する学科」、「国際関係に関する学科」については、特定の教科を1.5倍又は2倍した値をその教科の得点とみなすことができます。
理数及び国際関係に関する学科で特定教科の得点にかける倍率(令和7年度入試)
| 理数に関する学科 (数学・理科) |
学校名 | 学科名 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 船橋 | 理数 | 1.5 | |
| 柏 | 理数 | 1.5 | |
| 佐倉 | 理数 | 1.5 | |
| 佐原 | 理数 | 1.5 |
| 国際関係に関する学科 (英語) |
学校名 | 学科名 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 松戸国際 | 国際教養 | 1.5 | |
| 流山おおたかの森 | 国際コミュニケーション | 1.5 | |
| 成田国際 | 国際 | 1.5 | |
| 東金 | 国際教養 | 1.5 | |
| 市立松戸 | 国際人文 | 1.5 |
※木更津高校及び市立千葉の理数科については、数学及び理科の得点に、各高等学校が定めた倍率を用いることをしません。また、くくり募集を実施する理数科(市立銚子・成東・長生)も除きます。
特定の教科 「理数に関する学科」…数学及び理科 「国際関係に関する学科」…英語
また、三部制の定時制の課程で学力検査を5教科で実施した場合、5教科のうち、志願者が出願時に申告した3教科の得点を1~3倍した値をそれぞれの教科の得点とみなすことができます。(昨年度の倍率は全て1)
【調査書中の必修教科の全学年の評定合計値】
調査書の教科の学習の記録における、国語、社会、数学、理科、音楽、美術、保健体育、技術・家庭及び外国語(外国語については、必修及び全ての生徒が共通に履修するもの、現実的には英語)の評定の全学年の合計値(135点満点、45点×3年間)について、各高等学校が定めるKの数値を乗じ「調査書の得点」とします。Kの数値は、原則として1とし、各高等学校において学校の特色に応じて0.5以上2以下の範囲内で定めます。
調査書の得点 = 必修教科の全学年の評定合計値(135点満点)× K(0.5~2、原則1)
【調査書中の記載事項】
調査書中の記載事項(部活動、生徒会活動、資格など)について、各高等学校は学校の特色に応じて50点を上限として、上記の「調査書の得点」に加点することができます。
【学校設定検査の結果】
「学校設定検査の得点」の配点は、各高等学校が設定した検査数により決められています。
設定した検査数が1つの場合…………10点以上100点以下
設定した検査数が2つ以上の場合……合計得点の上限150点
※専門学科において適性検査を2つ以上実施し、さらに面接を実施する場合には、面接の配点は50点を上限とし、かつ学校設定検査の合計得点は200点を超えないものとします。また、学校設定検査を「その他の検査のうちの県が作成した思考力を問う問題」にした場合の配点は、100点とします。
基本的選抜方法
| 学力検査 | 調査書中の | 学校設定検査 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学年の評定合計値 | 記載事項 | |||
| 100×5教科 500点 理数に関する学科 (数学・理科) 国際関係に関する学科 (英語) 1.5倍又は2倍可 |
135点 × K K=0.5~2 原則1 |
0~50点 県大会出場など 英検・漢検など 生徒会役員など |
[1検査] 10点~100点 [2検査以上] 上限150点 *適性検査2つ以上+ 面接実施の場合は、 面接50点まで、 合計得点の上限は200点 |
◎◎◎点 |
| 〇〇〇点 | △△△点 | □□点 | ◇◇点 | |
イ 2段階による選抜方法(令和7年度入試では、全日制の約10%がこの選抜方法を導入しました。)
一般入学者選抜では、上記の「基本的選抜法方」に加えて各高等学校の特色を重視した選抜を行う、といった2段階の選抜を行うことができます。2段階の選抜を行う場合は、2段階目で選抜する人数は、募集人員の20%以下としなければなりません。
令和7年度入試で「2段階による選抜方法」を導入した学校・学科(17校22学科)
| 学校名 | 学科名 |
|---|---|
| 千葉 | 普通 |
| 若松 | 普通 |
| 幕張総合 | 総合学科 |
| 市立習志野 | 普通 |
| 市立船橋 | 普通 |
| 松戸六実 | 普通 |
| 学校名 | 学科名 |
|---|---|
| 市立松戸 | 普通 |
| 四街道 | 普通 |
| 佐原 | 普通・理数 |
| 東金商業 | 商業・情報処理 |
| 一宮商業 | 商業・情報処理 |
| 大原 | 総合学科 |
| 学校名 | 学科名 |
|---|---|
| 安房 | 普通 |
| 木更津 | 普通・理数 |
| 君津 | 普通 |
| 袖ケ浦 | 普通 |
| 袖ケ浦 | 情報コミュニケーション |
| 京葉 | 普通 |
2段階目の選抜では、1段階目の基本的選抜方法で得点(数値)化した【学力検査の成績】、【調査書中の全学年の評定合計値】、【調査書中の記載事項】及び【学校設定検査の結果】に、次のk1、k2、k3又はk4の数値を乗じた得点を、選抜の資料とすることができます。
k1 … 調査書中の全学年の評定合計値にKを乗じた数値に乗じる係数
k2 … 調査書中の記載事項の加点に乗じる係数
k3 … 学校設定検査の得点に乗じる係数
k4 … 学力検査の得点(特定教科の傾斜配点も含む)に乗じる係数
k1、k2及びk3の数値は、それぞれ1以上とし、各高等学校が定めます。またk1、k2及びk3を乗じた後の各資料の配点は、「基本的選抜方法」のそれぞれの上限を超えないものとします。また、k4の数値については、1以上1.5以下とします。
調査書中の全学年の評定合計値の上限…Kの数値が2の場合の270点
調査書中の記載事項の上限………………50点
学校設定検査の得点の上限………………1検査の場合100点、2検査以上の場合150点
適性検査2つ以上+面接の場合200点
2段階による選抜方法の例/A高校 普通科 募集人員280名
●1段階目の選抜(基本的選抜方法) 募集人員の80%、K=1、学校設定検査:面接
次の表の各資料の配点及びそれらを合計した総得点に基づいて、募集人員の80%(224名)までを選抜します。
| 学力検査 | 調査書中の | 学校設定検査 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学年の評定合計値 | 記載事項 | |||
| 各教科100点 × 5 |
135点×K(1) | 25点を上限に加点 | 面接官3名 各10点×3 |
690点 |
| 500点 | 135点 | 25点 | 30点 | |
●2段階目の選抜(学校の特色を重視した選抜方法) 募集人員の20% k1及びk2=2、k3=3、k4=1.5
募集人員の残り20%(56名)については、次の表の各資料の配点及びそれらを合計した総得点に基づいて選抜します。
| 学力検査 | 調査書中の | 学校設定検査 | 総得点 | |
|---|---|---|---|---|
| 全学年の評定合計値 | 記載事項 | |||
| 各教科100点 × 5 × k4(1.5) |
【135点×K(1)】
× k1(2) |
25点 × k2(2) |
30点 × k3(3) |
1,160点 |
| 750点 | 270点 | 50点 | 90点 | |
2.追検査(インフルエンザ罹患等への対策)
(1)受験資格
インフルエンザ罹患等による急な発熱で別室での受検も困難である等、やむを得ない理由により本検査又は一部を受検することができなかった者を対象とします。
(2)連絡、提出書類及び提出先
追検査を志願する者の在籍する中学校の校長等は、追検査受検願等の提出期間の前日までに、当該志願者の志願した高等学校の校長に電話により連絡しなければなりません。
また、追検査を志願する者は次の書類を、志願した高等学校の校長に提出しなければなりません。
- ・本検査出願時に交付された受検票
- ・追検査受検願
- ・本検査を受検することができなかった理由を証明する医師の診断書
- ※医師の診断書を提出できない場合には、在籍中学校の校長が作成した本検査不受検理由証明書を在籍中学校の校長の確認を経て、志願した高等学校の校長に提出します。
(3)検査の内容
5教科(国語・数学・英語・理科・社会)又は3教科(国語・数学・英語)の学力検査を、本検査とは別の問題により実施します。学力検査の時間は、国語・社会・数学・理科は各50分、英語は60分とし、配点は各教科100点とします。国語の問題は放送による聞き取り検査を含み、英語の問題は放送によるリスニングテストを含みます。 学校設定検査の実施については学校ごとの裁量とし、実施する場合にあっては、本検査に準じた学校設定検査を実施します。検査は1日のみで実施されます。
※本検査一部未受検者は、当該の教科等のみを受検します。
追検査の時間割
| 5教科の学力検査を実施する高等学校 | 3教科の学力検査を実施する高等学校 | ||
|---|---|---|---|
| 時 間 | 検 査 等 | 時 間 | 検 査 等 |
| 8:45 | 集 合 | 8:45 | 集 合 |
| 8:45~ 8:50 | 受付・点呼 | 8:45~ 8:50 | 受付・点呼 |
| 8:50~ 9:00 | 注意事項伝達 | 8:50~ 9:00 | 注意事項伝達 |
| 9:05 | 検査室着席完了 | 9:05 | 検査室着席完了 |
| 9:10~10:00 | 国 語 | 9:10~10:00 | 国 語 |
| 10:15~11:05 | 数 学 | 10:15~11:05 | 数 学 |
| 11:20~12:20 | 英 語 | 11:20~12:20 | 英 語 |
| 12:20~13:00 | 昼食・休憩 | 12:20~13:00 | 昼食・休憩 |
| 13:10~14:00 | 理 科 | 13:05~ | 学校設定検査(学校裁量) |
| 14:15~15:05 | 社 会 | ||
| 15:20~ | 学校設定検査(学校裁量) | ||
(4)追検査の選抜結果
追検査の選抜結果については、本検査の結果と併せて発表されます。